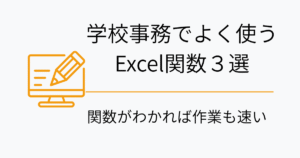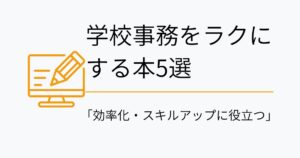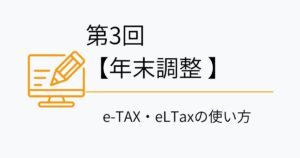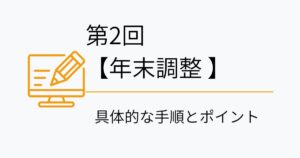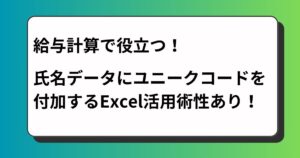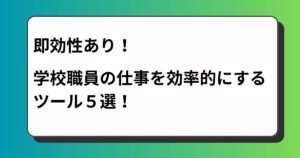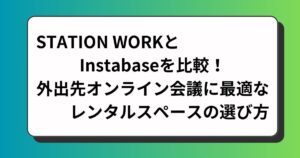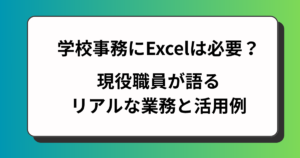シリーズ第1回目の学校事務職員が知っておきたい年末調整の基礎と実務です。
「年末調整って、一体何から手をつければいいのか分からない。」
学校事務職員として異動してきたばかりの方や、年末調整に関わるのが初めての方にとって、年末調整は大きなハードルに感じるものです。
しかし、年末調整の目的と流れ、必要な書類、対象者の基本を理解しておくだけで、業務の見通しが立ち、慌てず対応できるようになります。
この記事では、中学高校の学校事務職員が知っておくべき年末調整の基礎知識と流れを、初心者にもわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、何を準備し、どのような順序で進めればよいのかが具体的にわかるようになります。
年末調整業務への苦手意識をなくし、スムーズな準備を始める一歩を踏み出しましょう。
🟩 【結論】学校事務の年末調整、まず理解すべき結論
学校事務職員が年末調整を担当する際は、年末調整の目的・流れ・必要書類・対象者の基礎知識をまず押さえることが大切です。
全体像を理解しておくことで、慌てず確実に年末調整業務を進められます。
🟩 【理由】なぜ学校事務で年末調整の基礎知識が必要なのか
年末調整は、毎月の給与で仮計算されていた所得税額をその年の正しい所得税額に精算するための大切な業務です。
学校の場合、役員・常勤教職員・非常勤講師・臨時の職員など多様な勤務形態の職員がいるため、対象者の整理や提出書類の回収、内容確認が欠かせません。
後から訂正する作業は大変です。
12月給与時の年末調整で終わらせたい!
基礎知識があれば、書類回収漏れ・入力ミス・配布忘れなどのトラブルを防ぎ、結果的に業務負担を減らせます。
手引きを見ると嫌になる気持ちもわかりますが、基礎知識を持ちましょう!
🟩 【具体例・手順】学校事務で行う年末調整の流れと具体的なステップ
以下が学校事務で行う年末調整の基本的な流れです。
✅ 1. 年末調整の対象者を確認する
常勤教職員、年間を通じて勤務する非常勤講師などが対象となり、退職者などは対象外の場合があります。
- 常勤役員
- 非常勤役員
- 常勤教職員
- 非常勤講師
- 非常勤職員
- その他職員(臨時指導員等)
- などなど・・・
✅ 2. 必要書類を配布・回収する
- スケジュール感
- 11月中旬に周知・配布
- 11月下旬に提出期限
- 配布・回収書類
- 扶養控除等申告書(当年度分)
- 扶養控除等申告書(翌年度分)
- 保険料控除申告書
- 証明書貼り付け台紙(保険料控除証明書・国民年金控除証明書・確定拠出型年金控除証明書)
- 基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書
✅ 3. 書類内容を確認する
- 記入漏れ(続柄・署名・押印など)
- 控除額の記入内容が証明書と一致しているか
- 扶養人数の確認
✅ 4. 給与計算ソフト・Excel等へ入力する
ソフトの年末調整機能に基づき、回収した内容を入力。誤入力防止のためチェックリストを併用すると便利です。
✅ 5. 源泉徴収票を作成・配布する
年末調整後の確定した源泉徴収票を作成し、職員に配布します。
✅ 6. 市区町村への給与支払報告書提出
翌年1月末までに給与支払報告書を市区町村へ提出します(住民税関連手続き)。
🟩 【再結論】学校事務の年末調整、これだけ押さえれば大丈夫
年末調整は学校事務において避けられない重要業務ですが、流れと基礎知識を事前に理解しておけば落ち着いて進められます。
今回紹介した流れを参考に、まずは提出書類の管理・回収と確認体制を整えることから始めてみましょう。
次回の記事では、実際の入力手順・書類確認時のポイントなど具体的な実務編をお伝えします。