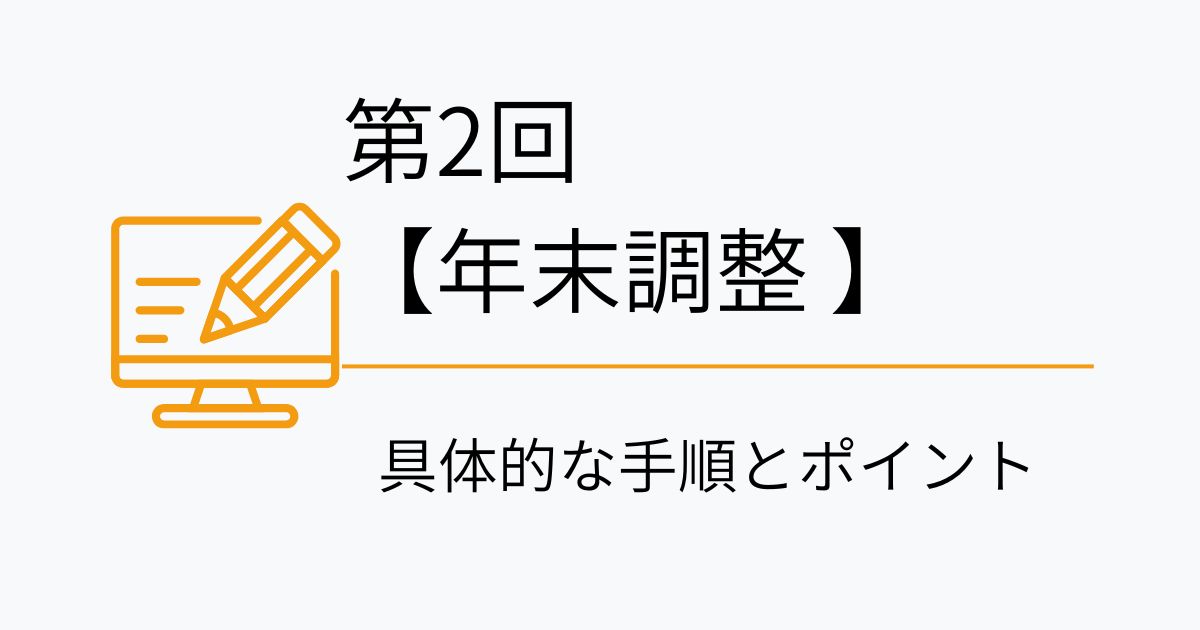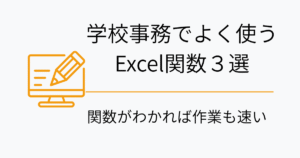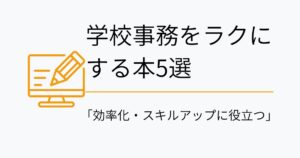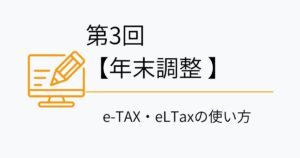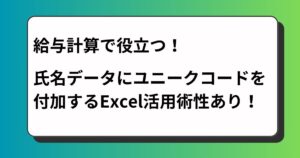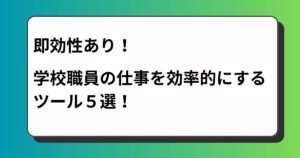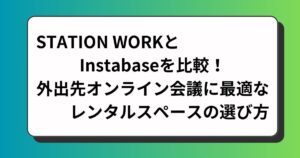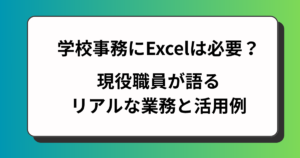📌 本記事は 令和6年(2024年)分の年末調整対応の内容です。年度によって控除額や記載内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
年末調整は学校事務の中でも避けられない大きな業務のひとつですが、「一体何から手をつければいいのか」「どんな流れで進めるとミスなくできるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に異動してきたばかりの学校事務職員や、年末調整を初めて担当する方にとっては、提出書類の種類の多さや確認ポイントの多さに戸惑うこともあるはずです。
この記事では、中学高校の学校事務職員が実際に行う年末調整の具体的な手順と押さえておくべきポイントをわかりやすく丁寧に解説します。
記事を読み終える頃には、何から始めればいいのかが具体的にわかり、年末調整の流れが頭の中で整理できるようになります。
ミスを減らし、スムーズに年末調整を進めるための一歩としてぜひ活用してください。
年末調整をミスなく進める最大のコツは「徹底したチェック」にあり!

年末調整を学校事務で担当する上で、最も大切なことは 「徹底したチェック」を行うことです。
年末調整は書類を配布・回収し、内容を確認して入力するという一連の流れがありますが、実際に大変なのは「集めること」以上に「内容が正しいかを確認すること」です。
扶養控除等申告書の記入漏れ、保険料控除証明書の添付漏れ、控除額の計算ミスなど、小さなミスが後から大きな修正作業に繋がり、結果的に多くの時間を取られる原因になります。
だからこそ、「提出された書類をチェックすること」「入力後に再チェックすること」を意識しながら年末調整を進めることが、最終的にはスムーズかつ短時間で終わらせるコツになります。
チェックを怠らないことが、学校事務職員が年末調整をミスなく乗り切る最大のポイントです。
年末調整を正確に行うための理由
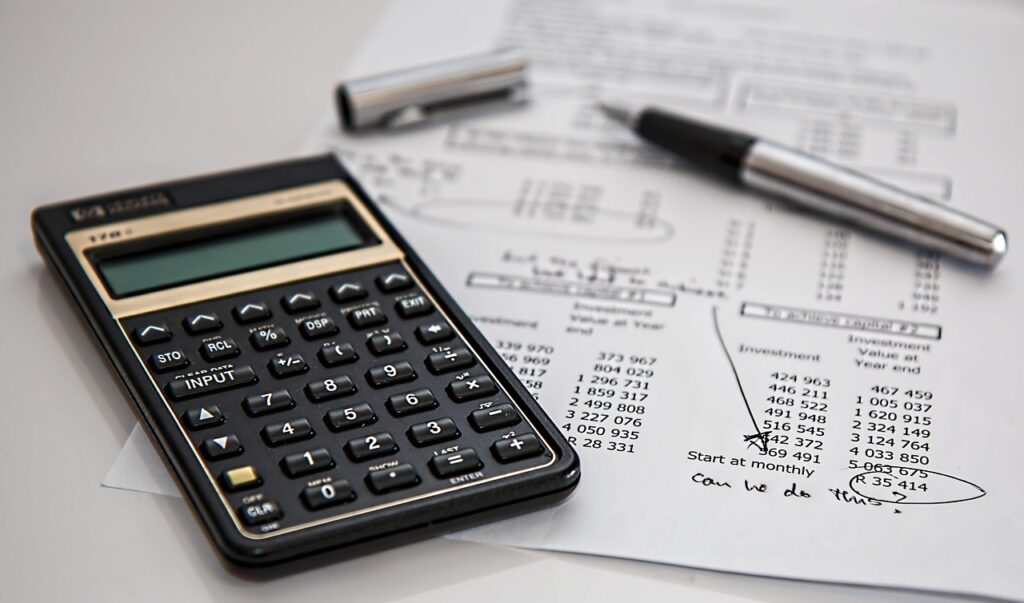
学校事務における年末調整業務は、単純な書類回収作業に見えて実は複雑です。
常勤・非常勤・臨時職員など雇用形態が多岐にわたり、回収すべき書類や控除証明書の種類も多く、記入漏れや記載ミスの確認が必要なため、思った以上に工数がかかる業務です。
さらに、年末は他の業務も多く重なる時期であり、計画性なく取り組むと直前で書類が集まらず焦ったり、入力漏れが発生したりして修正対応に時間を取られてしまいます。
だからこそ、あらかじめ具体的な流れとチェックポイントを知り、「何を」「いつまでに」「どう進めるか」をイメージして取り組むことが非常に大切です。
学校事務職員が実践する年末調整の具体的な手順と注意ポイント
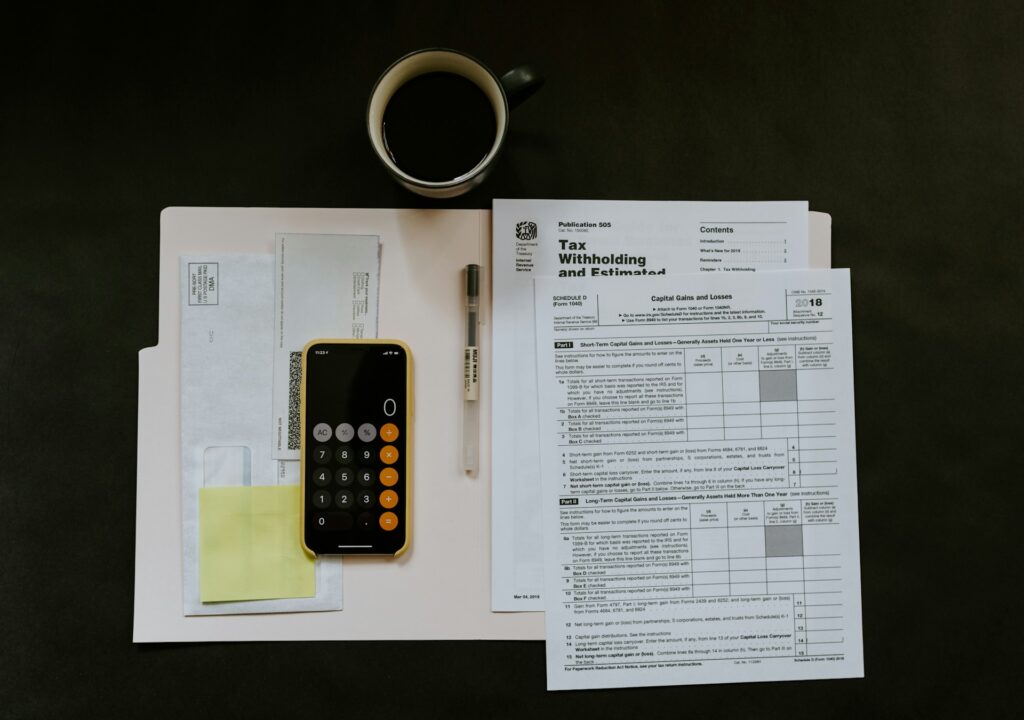
以下が学校事務職員が行う年末調整の具体的な手順と、それぞれのステップで意識しておくべきポイントです。
① 年末調整対象者のリストアップ
まずは年末調整の対象となる職員を整理します。常勤職員はもちろん、年間を通じて給与支給がある非常勤講師や臨時職員も対象になります。
年度途中の退職者、産休・育休中の職員の扱いについても予め確認しておきましょう。
リストアップから忘れてしまいそうな方
- 休職中で出勤されていない方
- 郵送またはWEBのやり取りになり、個別に対応することになる可能性があります。
- 季節変動で働いている方(特に年末調整時期に給与支給がない方)
- 退職ではなく、アルバイト的な働き方をしているので、忘れずに対応しましょう。
② 必要書類の準備と配布・提出依頼
扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書など、必要な書類を準備し配布します。
配布書類
- お知らせ
- 提出期限や対象者を記載しておきます。
- 郵送でのやり取りの方の提出期限は早めに設定しています。
- 中途退職者は源泉徴収票の提出依頼を記載しておきます。
- 住宅ローン控除がある方で初年分は
- 扶養控除等申告書(本年分)
- 既に提出されている申告書に異動があるか確認してもらいます。
- 扶養控除等申告書(翌年分)
- このタイミングで翌年分の申告書を提出してもらいます。その方がお互いラクです。
- 保険料控除申告書
- 書ききれない場合、2枚目にも記載し、合計額は1枚目に書いてもらいます。
- 添付台紙(保険、国民年金、確定拠出年金など証明書を添付)
- 台紙には職員コードと氏名を記載する欄を設けておきます。
- 管理しやすいA4用紙に統一するため、A4用紙の職員コード・氏名欄の下に枠線を入れ、この中に入るように添付するようにします。
- 複数枚の場合が多いので、右下に1/3(3ページの1枚目)のように記載する欄を設けます。
- 基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書
- 以前は、サンプルをお知らせに記載していましたが、税制が毎年変わり、複雑になるためURLを記載し、各自でアクセスさせるようにしました。
この際、提出期限を設定し、校内の職員にメールや掲示で周知を徹底することが大切です。
回収の段階で提出漏れが多発するため、回収リストを作成し管理することをおすすめします。
③ 書類回収後の内容確認
回収した書類の記入内容を確認します。
回収書類とチェックポイント
- 扶養控除等申告書(本年分)
- 扶養控除等申告書(今年分)
- 保険料控除申告書
- 金額に相違がないかチェックします。
- 介護医療を一般の生命保険に記載している等、勘違いが多いので記載箇所をチェックします。
- 添付台紙(保険、国民年金、確定拠出年金など証明書を添付)
- 控除証明書が本年分のかをチェックします。
- 契約時期によっては、提出期限までに証明書が届かない場合があります。その場合には、先に記載してもらい、証明書は後日提出してもらいます。
- 国民健康保険料の添付は不要ですが、国民年金保険料の控除証明書は必須です。
- 配偶者控除等申告書
- ここでは 「配偶者の所得が大まかにしかわからないんだけど…」 という質問が多いです。
- これについては 「今年も終わってないわけですし、確定していません。年間見込み額でOKです」 と伝えています。
- ただし大きく異なる場合には確定申告で修正が必要になることは伝えましょう。
- 基礎控除の欄で、「自分の収入がわかりません」と言う人がたまにいらっしゃいます(# ゚Д゚)
- この場合は前年分を参考にするか、今年の給与額から見積もるかして助けてあげましょう。。。
- 所得金額調整控除額は、基礎控除申告の際の給与所得の計算に必要になります。
- ここでは 「配偶者の所得が大まかにしかわからないんだけど…」 という質問が多いです。
- 源泉徴収票
- 本年分であるかチェックします。
- 住宅ローン控除申告書
- 本年分であるかチェックします。
- ペアローンの場合、備考欄に連帯債務者の必要事項の記載があるか確認します。
- 住宅ローン控除証明書
④ 給与システムの入力・インポート作業
ミスが起こりやすい作業のため、必ずダブルチェックを行い、入力後は仮計算をして過不足額の確認をしておきましょう。
給与システムの登録情報の更新・チェック
- 現住所と住民税課税地
- 【更新】
- 給与システム内の地区登録設定
- ①現支払い地区:6月~翌年5月まで支払う住民税支払い地区の地区を登録
- ②現居住地区:今住んでいる市区町村の地区を登録
- 給与システム内の地区登録設定
- 【チェック】
- Excelに出力し、差異をとる
- 市区村長からきている住民税表をもとに読み合わせを行う
- 【更新】
- 源泉徴収票の摘要欄
- 【更新】
- 住民税の普通徴収者には摘要欄に普A~普Fの符号を記載します。
- 普B「他の事業所で特別徴収」 → 乙欄該当者
- 普D「給与の支払いが不定期」 → 臨時職員(アルバイト・パート)
- 普F「退職者、退職予定者、休職者」 → 3月退職予定者
- 住民税の普通徴収者には摘要欄に普A~普Fの符号を記載します。
- 【チェック】
- Excelに出力し、紙でチェックします
- 乙欄=普Bとなっているか
- 臨時職員=普Cまたは普D
- 退職予定者=普F
- 休職者=普F
- Excelに出力し、紙でチェックします
- 【更新】
支払調書
忘れてはいけないのは、弁護士や社会保険労務士等に作成する支払調書です。
- 弁護士
- 税理士
- 社会保険労務士
- その他に報酬を支払った方
同じ給与システムで作成できるのであれば、忘れることもないと思います。
また、郵送日数を考慮し、本年中の支払いが確定した段階で早めに作成しておきましょう。
⑤ 源泉徴収票の作成・配布準備
年末調整完了後、確定した内容をもとに源泉徴収票を作成し、配布できる状態にします。
⑥ 書類の整理・次年度に向けた準備
回収した書類や控除証明書は学校で一定期間保管する必要があるため、年分ごとにまとめて保管します。
また、今年の年末調整での改善点をメモしておき、翌年度に活かせるように備忘録として残しておくと、次回の作業効率化に繋がります。
最後に
年末調整は学校事務職員にとって避けることのできない大切な業務ですが、流れとチェックポイントを事前に理解し、具体的な進め方をイメージしておくことで、焦らずスムーズに進めることができます。
本記事を参考に、まずは対象者の整理と書類配布から始め、丁寧に書類回収・確認作業を進めていきましょう。
これにより、年末調整業務に対する苦手意識が減り、自信を持って担当できるようになるはずです。
次回予告
次回の記事では、「第3回:学校事務職員が知っておきたいe-Tax・eLTAXの使い方【年末調整後の提出編】」について解説します。
ぜひ次回もチェックしてください。